前回の続きです!
前回は移動日から学会初日までの感想です。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://nandemoya-me.com/jace29-1]
第29回日本臨床工学会参加の感想
3日目(5月19日学会2日目)
前日の打ち上げで飲みすぎた体を引きずり、学会2日目の朝早くに行なっている日本臨床工学技士会の総会に途中からですが参加しました。
事業内容からシープリン運用まだと多岐にわたっておりました。
専門臨床工学技士に対する合格率についての意見があり、今後の協議課題として受け止めているとの回答がありました。
この辺りは今後何らかのアクションがあるのかなと思っています。
そして、2日目に聞きたかった「医師の働き方改革」における臨床工学技士の役割のパネルディスカッション!
今後自分たちの職域拡大や働き方も変わる可能性がある話題ということもあり大きい会場でしたがそれなりに人が入っていたこともあり、みんな気になるところなんだなと思いました。
「医師の働き方改革」における臨床工学技士の役割
現在、四病院団体協議会の「病院医師の働き方検討委員会」で医師の包括的指示による看護師業務の拡大など、医師から臨床工学技士をはじめ看護師・救急救命士・薬剤師の計4職種に対してタスクシフティングに関する提案がなされています。
タスクシフティングについて話し合うなかで臨床工学技士が認められている診療補助行為が重要になってきます。
臨床工学技士による診療補助行為の種類
- 医療機器及び回路等の準備
- 医療機器及び回路の組み立て・洗浄など
- 医療機器の操作に必要な薬剤・治療材料などの準備
- 医療機器先端部の接続または抜去
- 医療機器の運転条件・監視条件の設定および変更
- 医療機器の操作に必要となる薬剤の投与量などの設定および変更
- 医療機器(遠隔モニタリングも含む)による患者の監視及び観察
- 医療機器の操作ならびに患者の監視に関する記録
- 医療機器の機能維持・治療効果の評価および診断補助
- 医療機器に関連した情報の収集と提供(患者への説明を含む)
- 在宅医療における医療機器の操作及び管理
- 医療機器使用中の患者に対する救命処置
- 医療機器の操作に必要となる処置など
- 医療機器の操作に必要となる医師の介助など
①~⑪までは臨床工学技士が医師の具体的な指示により実施する医療機器の操作とされています。
⑫~⑭は臨床工学技士が医師の具体的な指示により実施する医療機器の操作に付随する行為とされています。
また、④・⑫・⑭は一部領域の業務において疑義が生じる可能性もあるとされています。
これらを踏まえたうえで話し合いをされているようで、パネルディスカッションの内容を聞いていると、臨床工学技士が医師からタスクシフティングされる領域は以前技士会からのお便りであったように周術期や心・血管カテーテル領域などの分野が多くなりそうな印象でした。
また、登壇された先生からは簡単に職域が広がるというのではなく、今まで医師ばかりの責任だったのががこちら(臨床工学技士側)にも負うようになっていくと話されていました。
現在は4職種に対して検討をされていますが、他の職種も職域拡大に向けて動き出しており今後の動きにも注目です。
最後に
今回の学会でいろいろな人に合ったり、様々な発表が聞けてすごく勉強になりました。
今後自分の働いている施設に生かせそうなことや今度はこんなことしてみたいなど思えてくるようなこともあり、やっぱり外の世界を知るというのは非常にいい経験になるなと思いました。
2020年の日本臨床工学会は愛知県の名古屋での開催予定との事なのでそちらも参加できるよう調整していきたいと思います!
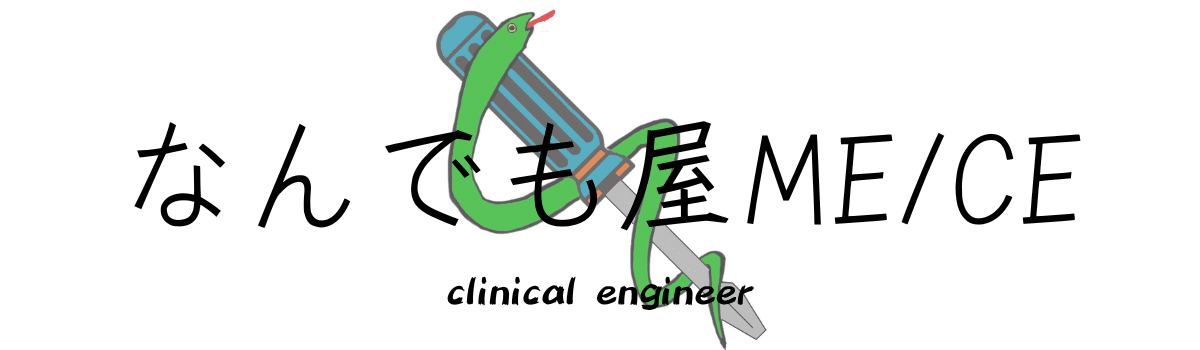
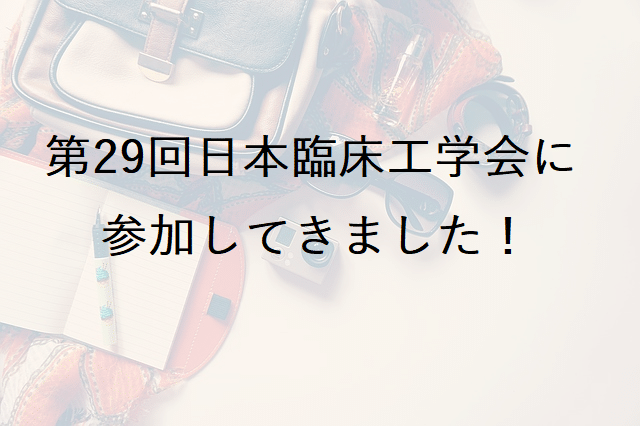
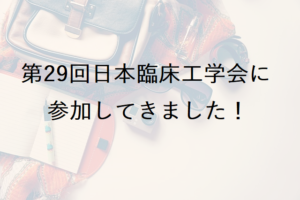
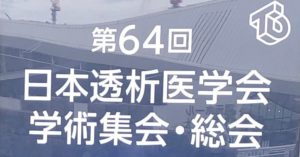
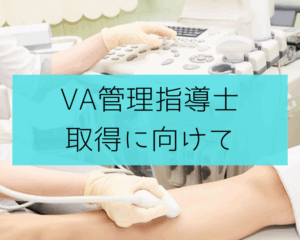

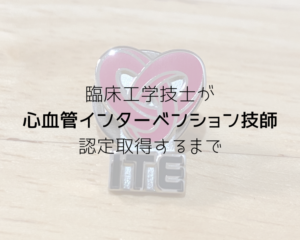
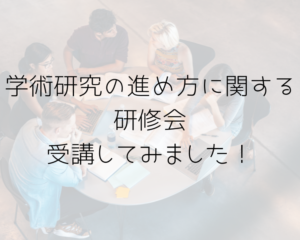
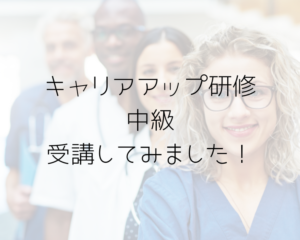
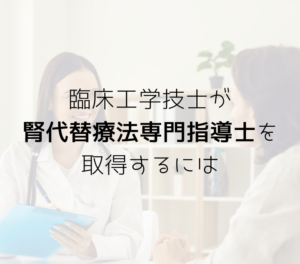
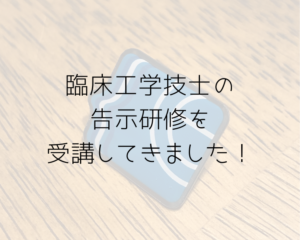
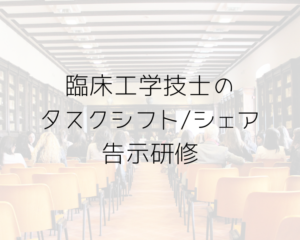
コメント