学術活動を行うにあたって、自分の場合はノウハウを教えてくれる人、いわゆる指導者がいませんでした。
そんななか、がむしゃらにやったのがたまたま論文掲載されましたが、講評で「論文や研究の基礎を学びなさい」と助言がありました。
指導者がいない中で出来ることは、研究に関してのセミナーを受けることが一番身につくだろうと考え、日本臨床工学技士会主催の「学術研究に関する研修会」を受講することにしました。
学術研究の進め方に関する研修会
費用:会員 8,000 円 非会員 12,000 円
「臨床工学技士認定制度」に係る本研修会取得単位は、10 単位となります。
受講内容
- 研究倫理
- 参考文献の集め方・読み方
- 研究デザインの作成
- 統計解析1 初級
- 統計解析2 中級
- 論文作成
- 臨床研究の実際1
- 臨床研究の実際2
投稿時の研修会内容は上記になっています。
資料はPDFダウンロードとなっており、郵送は有りませんでした。
 アレグ
アレグ単元ごとのダウンロードで少し面倒でした。
E-ラーニングとなっており、好きな時間に学べるのがよかったです。
PDF資料のためタブレット端末に落としてからPCで再生させる手法をとりました。
受講しての感想
全体的に非常にためになる内容でした。同時期に都道府県技士会主催の同じような研修も受けており、同じことを説明されていたのでこれがゴールデンスタンダードなんだなと改めて感じることもありました。
統計解析2 中級ではデータベースを自作して自分でEZRを起動させ処理を実行させる内容でした。
個人的にはハンズオンも大事だと思いますがEZRを使用しない方もおられるのでこういった事よりも、どんな研究にはこのような統計解析手法を用いるなどそういった事を教えてもらうとありがたかったかなと思いました。
初級で上記は触れられているのですが、代表的なt検定やマンホイットニーU検定などしか触れられていないので、3郡以上やロジスティック回帰などは触れられていませんでした。
この辺りを少し期待していたのですが、技士会の研修で統計研修もあるのでそちらで詳しくされるのかなと思いました。
個人的に大変ためになったのが、倫理員会での書類作成に関わることや実際に臨床研究をされて論文発表までされた方のノウハウを教えていただけたことです。
僕が論文投稿の際に、査読者から指摘された注意事項が解説されていたので、きちんと読んでくれていたんだなと改めて思いました。



繰り返し使用する似たような用語は統一するなど、基本が出来てなかった…
今後、技士会では生涯教育システムが再構築されるようです。
そのなかで、ステップアップコースとして教育研究がありこの研修はそこにあたる物だと思います。
臨床上で研究まで行わないにしても、論文の読み方やデータの示し方がわからなければ効果的な治療を提供できない恐れもあると思います。
例えばメーカーなどから医療機器等の説明を受けた際に、セールストークに騙されず「本当の効果」を知るためにこれらは必要な知識ではないでしょうか。
少しお高い研修費ですが、僕のように指導者がいない方や研究手法をきちんと学びたい人にはもちろんですが新人研修の一環としてもお勧めだと感じました。
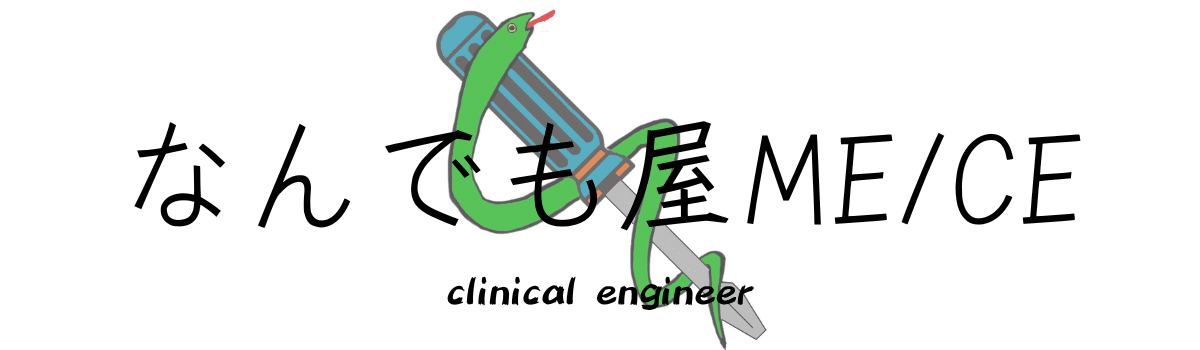
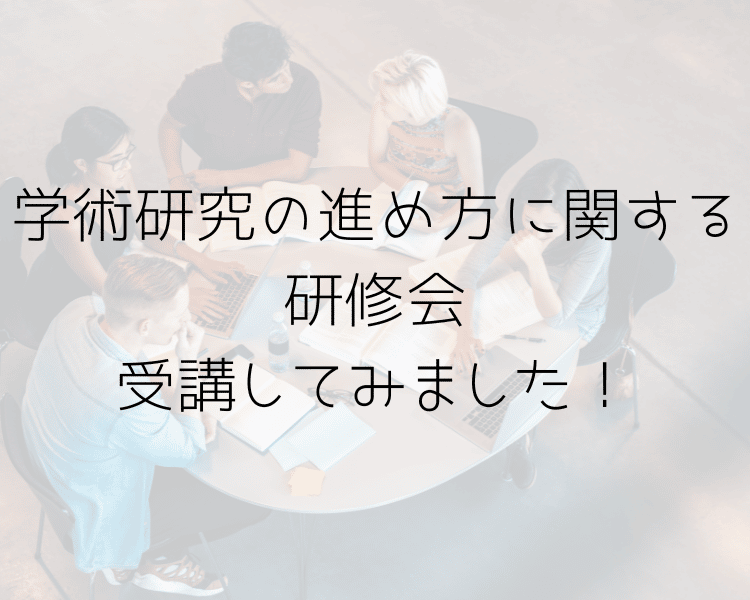
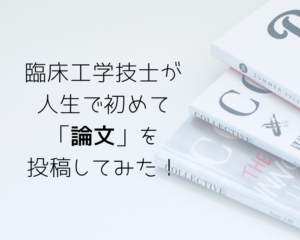
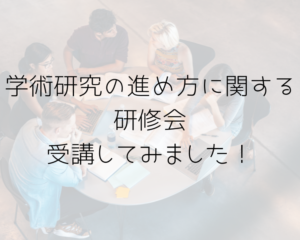
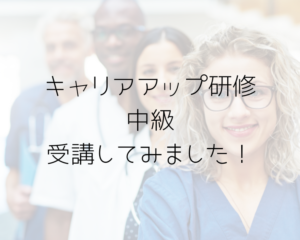
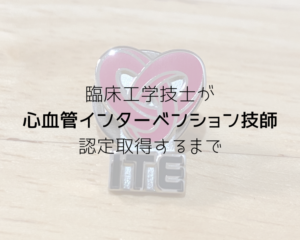

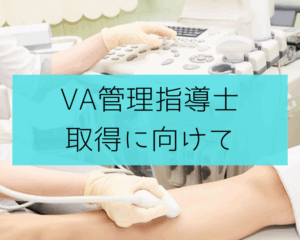
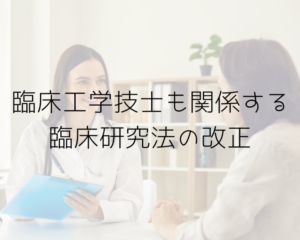
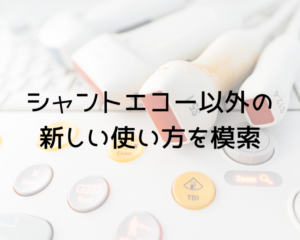
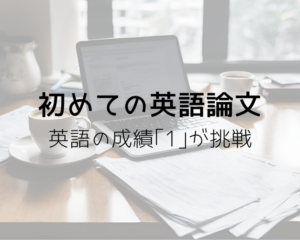

コメント