今回はペースメーカーのコードについて解説していきます。
ME2種や臨床工学技士国家試験の問題にも出てくるので学生の方はよく覚えておきましょう!
ペースメーカのコード
NBGコードとは
現在ペースメーカの作動様式を表すものとして3文字~5文字のアルファベットで表されるNBGコード(NASPE/BPEG Generic Pacemaker-Code)と呼ばれるもが使用されています。
教科書やペースメーカー手帳に書かれているモードで、VVIなどと書かれているのがこのNBGコードを使った作動様式を表しています。
各コードの意味
第1文字
第1の文字(例:AOOならAの部分)はペースメーカによる「電気的刺激」を行う部位を示しています。
- A(Atrium):心房
- V(Ventricle):心室
- D(Dual):心房及び心室
- O(None):ペーシング機能はない
第2文字
第2の文字(例:AOOなら真ん中のOの部分)はセンシング(自己心拍の検出)をする部位を表します。
つまりペースメーカが自己心拍を「見ている」所を表しています。
- A(Atrium):心房
- V(Ventricle):心室
- D(Dual):心房及び心室
- O(None):センシング機能はない
第3文字
第3の文字(例:VVIならIの部分)は自己心拍をセンシングした際のペースメーカの反応を表します。
- T(Triggered):同期(自己心拍に同期してペーシングを行う)
- I(Inhibited):抑制(自己心拍を確認してペーシングを行わない)
- D(Dual):同期と抑制を両方行う
- O(None):同期と抑制を行わない
第4文字
第4の文字(例:DDDRならRの部分)はレート応答機能の有無を表します。
- R(Rate Modulation):レート応答機能があることを意味する
- O(None):レート応答機能がない
第5文字
第5の文字はマルチサイトペーシング機能の有無を表します。
- A(Atrium):心房マルチサイトペーシング機能あり
- V(Ventricle):心室マルチサイトペーシング機能あり
- D(Dual):心房及び心室マルチサイトペーシング機能あり
- O(None):マルチサイトペーシング機能がない
 アレグ
アレグ5文字目はちょっと特殊です!
NBGコードまとめ
| 第1文字 | 第2文字 | 第3文字 | 第4文字 | 第5文字 |
| ペーシング(刺激)部位 | センシング部位 (自己心拍の検出) | センシング時の ペースメーカの反応 | レート応答機能 | マルチサイトペーシング機能 |
| A(Atrium):心房 | A(Atrium):心房 | T(Triggered):同期 | R(Rate Modulation):あり | A(Atrium):心房 |
| V(Ventricle):心室 | V(Ventricle):心室 | I(Inhibited):抑制 | O(None):なし | V(Ventricle):心室 |
| D(Dual):心房・心室 | D(Dual):心房・心室 | D(Dual):心房・心室 | D(Dual):心房・心室 | |
| O(None):なし | O(None):なし | O(None):なし | O(None):なし |
基本的に第1~第4文字までが一般的に使用されます。
レート応答機能がある場合はDDDRといった様に記載され、ない場合はDDDと記載するのでわざわざDDDOと記載はされません。
最後に
これから少しずつですがペースメーカについても書いていこうと思います。
僕自身まだまだ勉強中で業者さんに頼ってばっかりの為、少しでも自分の武器としていきたいので「自分なりのノート」というような形で記事にしていきたいと考えています。
参考文献
第10回「CDR認定取得」を目指すための『業界指定講習会テキスト』Ⅱ (2016年) 臨床ペーシングの基礎 P27 日本CDRセンター
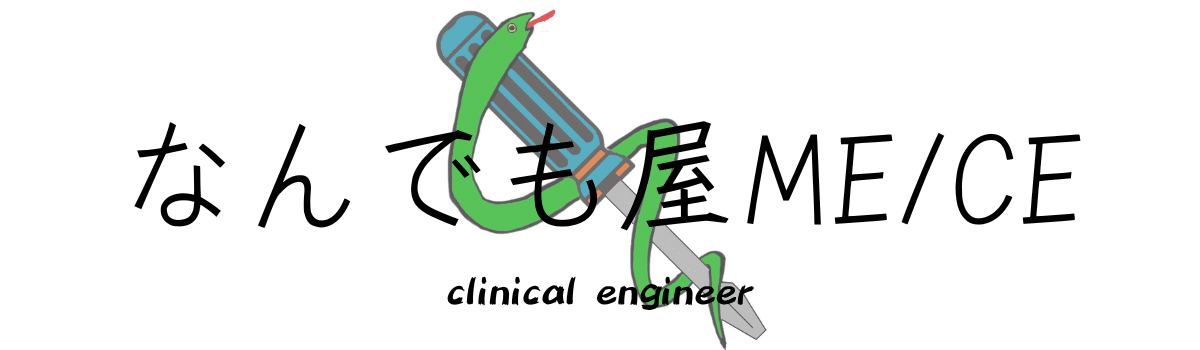
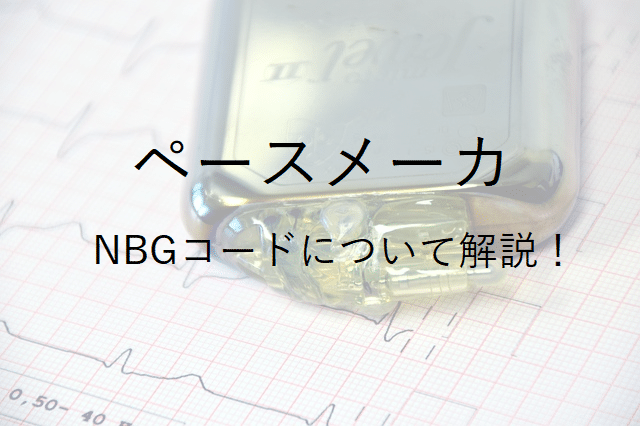
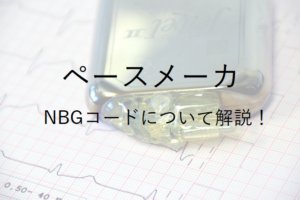
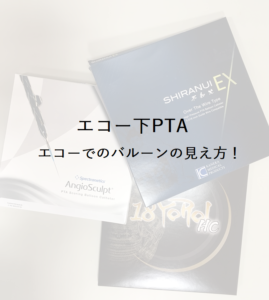
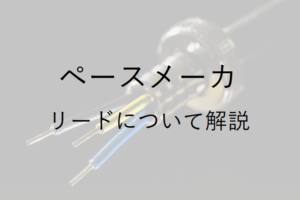
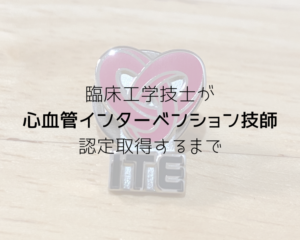
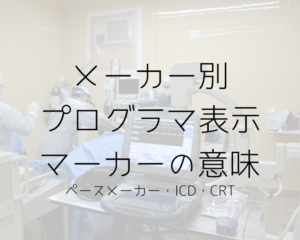
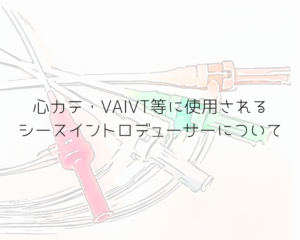
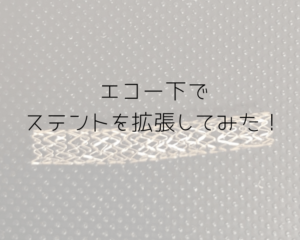
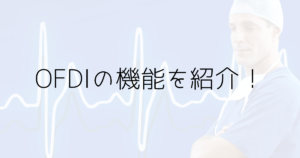

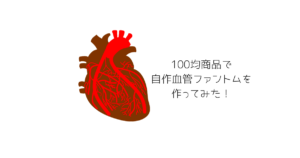
コメント
コメント一覧 (2件)
こんにちわ。
下記のtweetに、リンクさせて頂きました。
簡潔で分かりやすいブログ、参考にさせて頂いております。
https://twitter.com/NaokiThukishima/status/1278634985268736000
こちらも下記の心電図ブログを行っております。
お暇な時に、お立ち寄り下さい。
紹介していただきありがとうございます!