臨床研究において、論文を書くというのは非常にハードルが高いと感じます。
 アレグ
アレグ臨床業務をしながらなんて・・・
子育ても・・・
当たり前のようにされている、臨床工学技士の人たちを見ると世界が違うなーなんて思います。
臨床工学技士の養成校が大学ですと、卒業研究なんてものがあり実際に論文を書いたりすることもありますが、書き方なんてあまり教わってなかったような気がします。(筆者の場合)
ましてや「英語」となるとさらに難易度が上がります。
しかし、英語で論文を書くというのは大きな意味があります。
日本語を読める人口に対して英語を読める人口は大きく違うため、色々な人に見てもらう・読んでもらうためには「英語」で書くというのは非常に大きな意味があると思います。
今回、何を思ったか中学英語でさえ成績1を記録した筆者が英語での挑戦を決意し、投稿から掲載までできましたのでその過程を書いてみました。
英語論文の作成
最近ではChatGPTをはじめとする、AIを使うことにより簡単に日本語→英語の文章作成が容易となっています。
自分自身英語の能力はかなり低く、赤点ギリギリや赤点レベルの成績を維持していました。(維持とは・・・)
そんな自分がまともに英語を操れるわけがないので、AIは大いに活用させてもらいました。
今回使用したのは、下記のツールを使用。
- DeepL
かなり有名な翻訳アプリ。ブラウザでも可能。英語PDFなどもそのまま翻訳されるが、書式によってはおかしなことになる。
大まかに読む分には可能。 - Google翻訳
DeepLで英語化されたものを再度日本語に訳し、日本語としておかしくないかをチェック。 - NotebookLM
英語の文献を読み込ませ、日本語で質問し内容を聞き出したり、要約をお願いしたりできる。
複数の文献を読み込ませ、関連する情報の文献をピックアップするのにも使用。
文献の検索
メインはPubMedです。
他のツールとしては、Google Scholarを使用しました。
今回英語論文を投稿するにあたり、参考文献も英語にしなければならないのでは?と考え、日本語論文を探すのに使用しているJ-STAGEは使用しませんでした。
文献管理ソフト
初めて論文を書くと決めた時に購入した「EndNote」を使用しました。
個人で買うには勇気のいる金額ですが、それなりに活用しているので元は取れているような気がします。
他にも無料のソフトなどあり、そのようなものを使うのも方法の一つと思います。
なぜ文献管理ソフトが必要かというと、投稿先によって「参考文献」の書き方は違います。
それに対応した書き方でないと、投稿却下(reject)の可能性が高まるからです。
文献管理ソフトを用いれば、投稿先にあった参考文献の書き方に自動で変換してくれて、論文取り込み時に必要な情報(タイトルや著者名など)も自動取り込みができ、余計な時間を使わずに済むので論文投稿初心者こそ必要と感じています。
英文校正
今回は、「エディテージ」さん
選んだ理由としては、大手のサービス会社であること、カバーレターの作成、論文再校正となった場合のサポートが上限なし、といったことから選択しました。
プランも複数あり、選んだのは「プレミアム英文校正」にしました。
理由としては、カバーレターの作成などもオプションに含んでおり、1年間論文の再校正が無料となっていたからです。
再校正は、一発で投稿受諾となる自信があるのならスタンダードでも良いのですが、そんなことはほぼ起こり得ないので再校正が必ず行われるためこちらのプランにしました。
またオプションとして、グラフィック調整も依頼。
こちらは、投稿規定が正しく読み取れているか自信がなかったのと、投稿先がオープンジャーナルのため図などの書式がかなり詳しく決められていたのでお願いしました。
校正者とのやり取りが全て英語なためこちらも、論文投稿と同様に翻訳ソフトを使用して行いました。
うまくニュアンスは伝わっているようで、期待した指示通りの回答が得られていました。
→再校正で何度か英語のやり取りを行いましたが、こちらの指示がダメなのか意図が伝わっていない感じでした。
カバーレターに関しては書式が決まっているのか初回以外はほぼ毎回同じようなカバーレターとなっていました。
初回の提出
投稿先はオンラインでの提出を行っていました。
Chromeで行ったので、自動的に表示されるページの英語は翻訳されていたので、迷いはあまりなかったです。
ただ、適宜翻訳しないで確認する必要な作業もありました。
例:要旨文書の確認や、著者の情報入力など
投稿後の進捗状況も、著者用ページでわかるため「今どのあたりに進んでいるのだろう?」といったことがすぐにわかります。
4日程度で編集者からの決定が下されていました。
1回目の査読
だいたい1ヶ月も経たずに返ってきていました。
もちろん返事は「英語」です。
しかも返事を受け取ってから、2週間を期限として再提出を求められていました。
今までの投稿経験から2~3ヶ月くらいは猶予があると思い込んでいたので、すぐ査読対応に取り掛かることにしました。
幸い、内容的には「minor revision」のような感じでしたので対応自体はすぐに終わりました。
査読対応
まず査読者ごとに質問を分けました。
そして、各査読者への返答メモとしてその質問ごとに記載していきました。
例としてはこのような感じ。
査読者1
1. P8の180行目に書かれている単語は「〇〇」であるが、「××」の方が正しい。
P8の180行目の「〇〇」→「××」
すぐに修正箇所がわかりやすいように、文字をマーカーなどで変色させてました。
実際の返答ではこのように返しています。
査読者1
1. P8の180行目に書かれている単語は「〇〇」であるが、「××」の方が正しい。
大変失礼いたしました。P8の180行目の「〇〇」を「××」と変更させていただきました。



実際の返答は色を変えませんでした。
今思えば、変えても良かったかもと感じています。
これら作業を、すべての返答で行いました。
もちろん返答は「英語」・・・
査読対応後の校正
修正したらもちろん校正も必要。
査読後の校正は、他のところを変更してほしくないので修正箇所をマーカーで示して、示した場所のみを校正でお願いしました。
このマーカーを引く作業は、査読者への返答としても有効と感じているので、各査読者ごとに色は変えていました。
修正箇所にもよりますが、2日程度で修正完了していたのでスムーズに行えていたと思います。
2回目の投稿
1回目と同じやり方で投稿可能でした。
ですが、1回目の投稿時データがそのまま残っているので、一度全て消して再度投稿をし直す必要がありました。→一部は必要なしです。
追加箇所として、査読者への返答ファイルの要求があったのと、上記で述べた変更箇所のマーカーが無いファイルを修正論文として提出することになっていました。
マーカーで示したファイルは関連ファイルとして提出が可能であり、ファイルタイトルにhighlight:〇〇として投稿しました。
2回目の査読
内容的には、minor revision(軽微な変更)とされていました。1回目の査読に対して「著者は変更点に関してよく書けている。」といったコメントのみの査読者もおられ、返答すべきか悩みましたが「好意的なご感想をお寄せいただき、ありがとうございました。」と返答しました。
minor revisionの内容はスペルミスや使用機材の書き方についてです。
スペルミスは、校正かけてるのになぜ?と思いましたが・・・気づけなかった自分も悪いですが。
使用機材について、日本企業を英語表示に直した場合、Company Limitedの書き方が統一されていないようでした。
この辺りも校正で気がついてほしかったですが・・・
投稿ジャーナルもあまり統一性がないように感じられたので、「論文内での統一」を行いました。
〇〇株式会社、東京、日本
〇〇 Inc., Tokyo, Japan
〇〇株式会社、東京、日本
〇〇 Co., Ltd., Tokyo, Japan
これらに統一して表記しました。
再度の投稿に関しては、2回目投稿と同じ手順でした。
投稿結果
投稿から約4日程度で投稿結果についてのお知らせが!
結果は、無事「受理」!
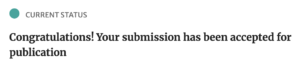
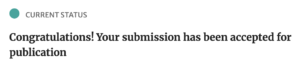
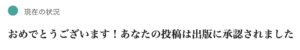
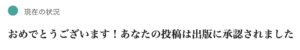
メールも送られてきており、掲載までの流れについて記載されていました。
- 編集部による書式を整える作業。
- 著者による最終チェック。(所属機関や、氏名のスペルなど確認を行うこと)
このチェックは、2営業日以内に行うこと。
これらが記載されていました。
著者による最終校正
2週間ほどで、最終校正のお願いが届きました。
自身初となる、オンラインでの著者校正でした。
指示が記載されており、著者・共著者の所属や住所が正確に記載されているかの確認でした。
これら指示は全て英語で説明されており、翻訳ソフトを駆使しなんとか提出までできました。
住所のところがあまり自信がなく、共著のドクターに聞いて助けを求めたりもしましたが、結果的にすでに掲載されている論文を参考に記載しました。
基本的には、番地, 町や郡, 市, 都道府県, 郵便番号, 国名となるようでした。
例:〒100-0000東京都〇〇市or区□□町12345
12345 □□-cho, 〇〇, Tokyo 100-000, Japan
掲載
校正を送った2日後には、掲載されました!というメールが届き、掲載されたんだ〜という実感が出ました。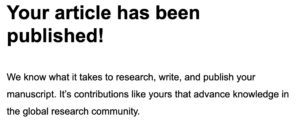
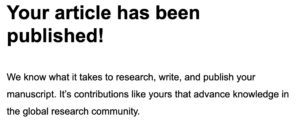
今回の投稿先はオープンアクセスのジャーナルなので、ネット上から閲覧やダウンロードができます。
Wordで書き上げたもの比べると、見違えるほど綺麗にレイアウトされて掲載されていました。
最後に
今回この論文投稿に携わってくれた関係者の方々にとても感謝いたします。
編集者、査読者の皆様には特にお世話になり、的確な指摘が大変ためになりました。
指摘に関する文章の言葉遣いに関して、救われる部分もありました。→あまり強く言われるとメンタル削られます・・・
次は原著を目指しつつ、研究と臨床頑張っていきたいと思います。
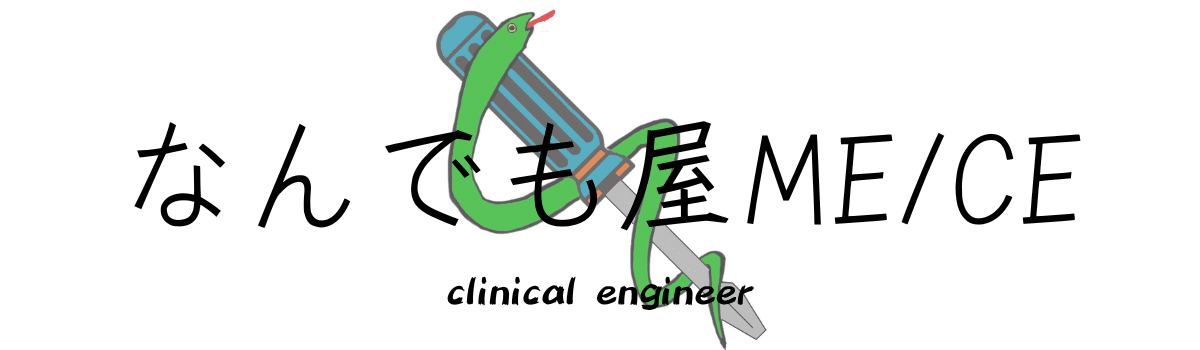
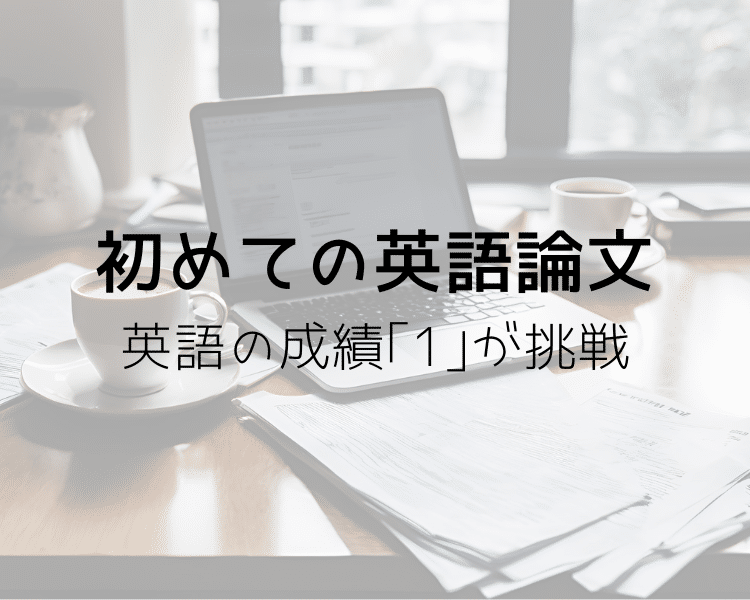
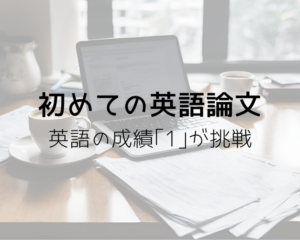
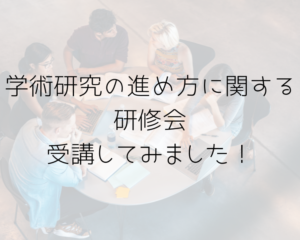
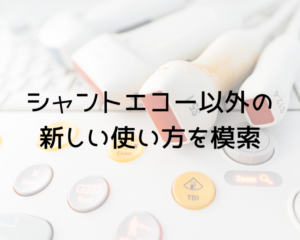

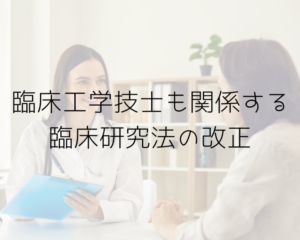
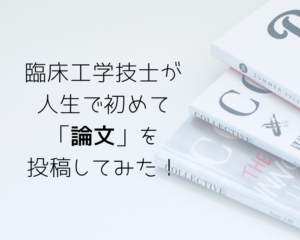
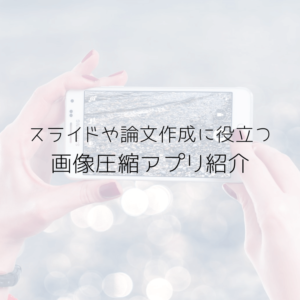
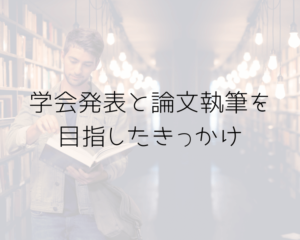
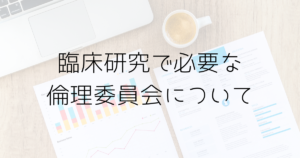
コメント